・薬剤師ってAIに代替されちゃうんじゃないの?
・AIについて興味があるけど、何から学べばいいの?
・薬剤師としてAIを活用したいけど、何ができるの?
昨今のAIブームで「薬剤師はAIに代替されてしまう職業なのではないか」「そろそろ自分もAIについて学ばないと」と危機感を感じている方が増えてきています。
そこで今回はAI学習に月70時間以上費やしているAIオタクの薬剤師が、今知っておくべきAIの基礎知識や薬剤師業務・自己学習での具体的なAI活用方法についてご紹介します。
この記事を読むと、AIを基礎から学ぶことができ、明日からの業務や自己学習に役立てるヒントが得られます。

それでは一緒に学んでいきましょう!
- AIをうまく活用することで、業務・自己学習の効率が格段に向上する。
- これから先、「AIを使える人」「AIを使えない人」の差がさらに広がる。
- まずは、「AIに触れてみる」ことから始めてみよう!
AIの歴史は意外と古い!《第4次AIブームの到来》
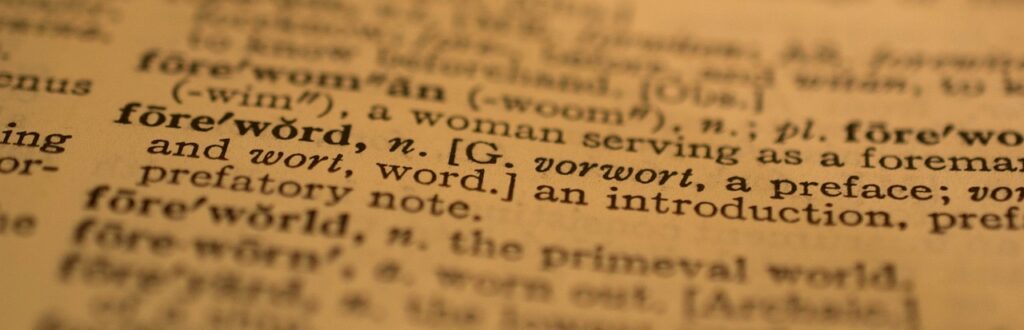
AIの歴史は意外にも古く、既に3回ものAIブームが到来しており、今回で4回目のAIブームだと言われています。これまでのAIブームでは技術的な限界が理由で、あまり盛り上がらずに終わりを迎えてしまいました。
ですが現在のAIブームでは、これまでのAIブームとは比べ物にならないぐらいの盛り上がりを見せています。その理由として、「実用的なレベルのAIが出現したこと」「技術者から一般人にいたるまで幅広く普及したこと」が挙げられます。

特に2022年に登場したChatGPTは「自然な対話能力」と「誰でも使える手軽さ」で第4次AIブームの火付け役となりました。
AIは大きく分けてANIとAGIの2種類ある
AIには大きく分けて「ANI(特化型AI)」と「AGI(汎用型AI)」の2種類があるとされています。初めて耳にする方が多いと思うので分かりやすく解説していきます。
ANI(特化型AI)とは、「特定のことだけが得意なAI」を指します。特徴として、一つの分野であれば人間以上の能力を発揮することが挙げられます。
AGI(汎用型AI)とは、「人間のように、いろんなことを柔軟に考えられるAI」を指します。特徴として、複数の分野をまたいで人間のように考えたり学んだりできることが挙げられます。
| 項目 | ANI(狭い知能) | AGI(汎用知能) |
|---|---|---|
| 得意なこと | 限定的な作業だけ | なんでも対応可能 |
| 例 | 囲碁AI、翻訳AI | 人間のような万能AI(未実現) |
| 実現状況 | すでに多数ある | まだ研究中・未来の話 |

AGI(汎用型AI)は2030年代に登場するのでは?と言われています。
AI初心者が知っておきたいAI用語
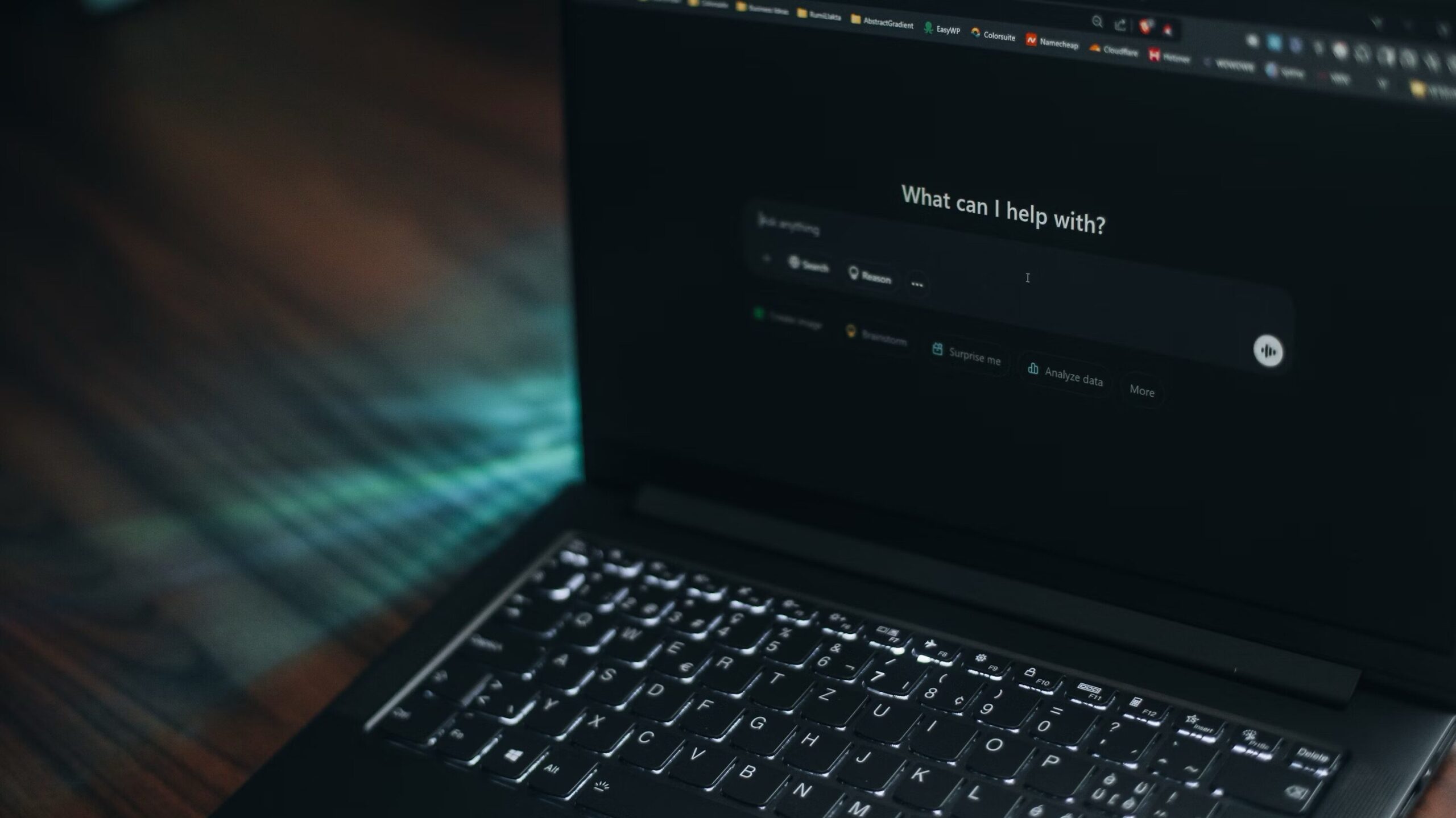
AIを学び始めると様々なAI用語が出てきます。そこでこの章では、AIを学び始めた初心者が知っておきたいAI用語を6つご紹介します。
機械学習(Machine Learning)
機械学習とは、AIが自分でデータから学習し、判断や予測ができるようになる仕組みです。人間がすべてのルールを教え込まなくても、大量のデータをもとにAI自身が「パターン」や「傾向」を見つけ出します。
たとえば、たくさんの「猫と犬の画像」を見せて、「これは猫」「これは犬」と正解を教えていくと、AIは次第に特徴を学び、初めて見る画像でも猫か犬かを判断できるようになります。使えば使うほど賢くなる点が大きな特徴です。
ディープラーニング(Deep Learning)
ディープラーニングは、機械学習の中でも特に高性能な方法で、2010年代以降のAIの急速な進化を支えた重要な技術です。特徴は「多層構造のニューラルネットワーク」を使って学習すること。
人間の脳の神経回路を模したネットワークを何層にも重ねることで、画像の中の「目・鼻・口」のような細かな特徴や、音声の抑揚、文章の文脈など、非常に複雑なデータを理解できるようになります。たとえば、顔認識、自動翻訳、自動運転などは、この技術によって実現しています。
ニューラルネットワーク(Neural Network)
ニューラルネットワークは、ディープラーニングの基盤となる構造で、人間の脳の神経細胞(ニューロン)を模したものです。複数の「層(レイヤー)」を通じて情報を段階的に処理し、画像や音声、テキストのパターンを抽出していきます。
この多層構造により、AIは単純なルールだけでは見抜けない複雑な特徴も理解できるようになります。ニューラルネットワークの進化が、今日の高精度なAIモデルを可能にしているのです。
アルゴリズム(Algorithm)
アルゴリズムとは、AIが「どのように学習し、判断するか」のルールや手順のことです。料理でいえば「レシピ」のようなもので、同じ材料(データ)を使っても、アルゴリズムが違えば、まったく別の結果(モデル)が生まれます。
たとえば、同じ文章データを使っても、「分類する」のか「文章を作る」のかによって使うアルゴリズムは異なります。よって目的や扱うデータに応じて、最適なアルゴリズムを選ぶことが重要です。
モデル(Model)
モデルとは、AIが学習した結果として作られた「判断の仕組み」のことです。学習用のデータを使って、アルゴリズムに従って訓練され、特定のタスク(たとえば画像分類、文章生成、音声認識など)をこなせるようになったAIの完成形ともいえます。
実際にAIが何かを「判断する」「生成する」といったときには、このモデルを使って処理が行われています。モデルは目的ごとに作り分けられ、使うデータや学習方法によって性能が大きく変わります。
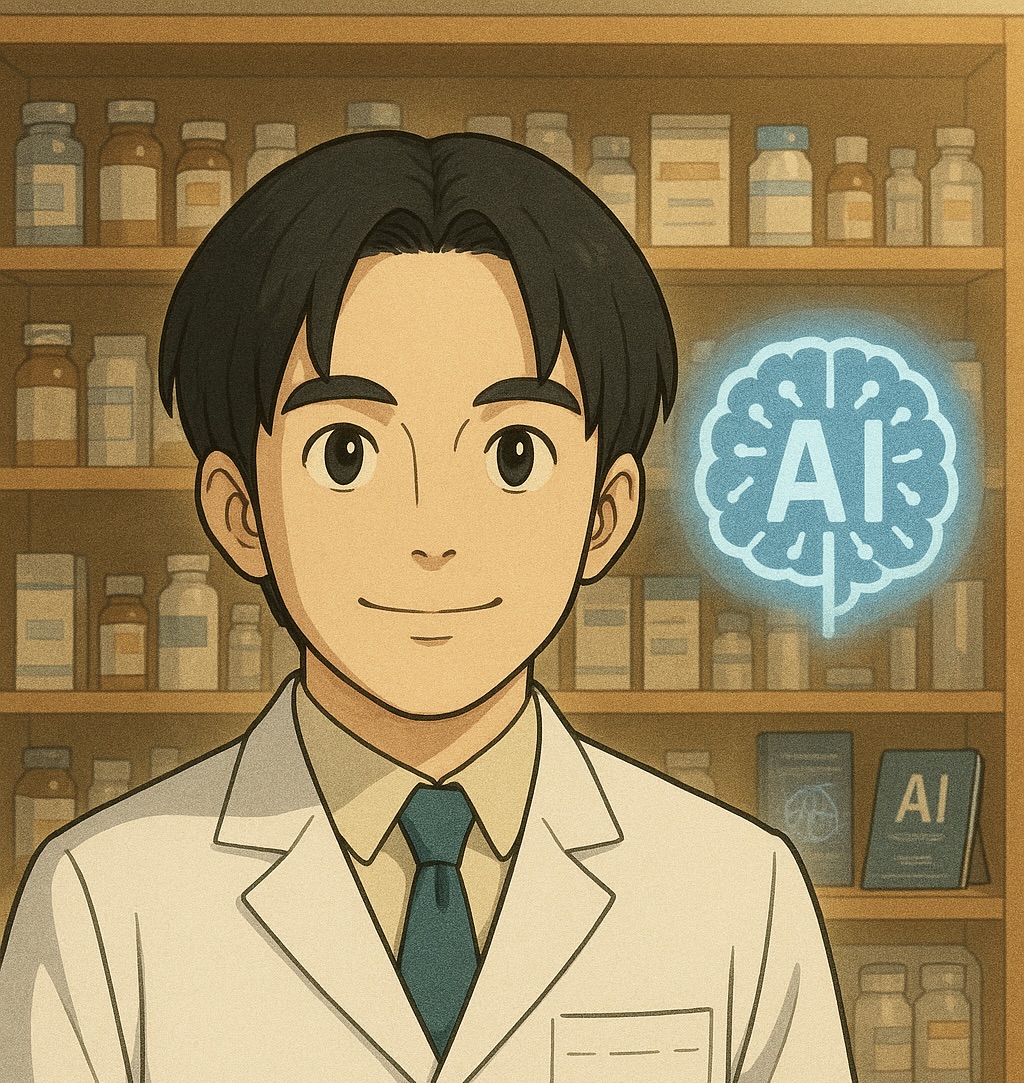
つまり「モデル」=「AIの頭脳」ということですね。
パラメータ(Parameter)
パラメータは、AIモデルの中で調整される数値のことです。モデルが学習を通して「データのどこに注目するか」や「どの程度重みをつけるか」を決定するために使われます。
たとえば、画像認識のAIなら、「耳の形に注目する比重」や「背景の影響をどれくらい無視するか」といった人間で言うところの感覚に相当します。ディープラーニングでは、このパラメータが数百万〜数十億個にも及ぶことがあり、それだけ複雑で柔軟な判断ができるようになります。
AIを使う上で注意しておきたい4つのこと

AIはとても便利で、うまく使えば大きな助けになります。ですが「使い方」や「注意点」を知らずに使うと思わぬトラブルにつながることもあります。そこでこの章では、AIを使う上での注意点を4つご紹介します。
AIは「正解」を保証するわけではない
AIが出した答えは「最も可能性が高い答え」であって、必ずしも正しいとは限りません。たとえば、AIに薬の情報を聞いた場合、最新の内容や正確な根拠が含まれていないこともあります。
なのでAIから得た情報は、鵜呑みにせずに一度自分で確認するクセをつけましょう。たとえば「出典はどこか?」「いつの情報か?」など、ネット検索や専門サイトで裏取りをすることが大切です。
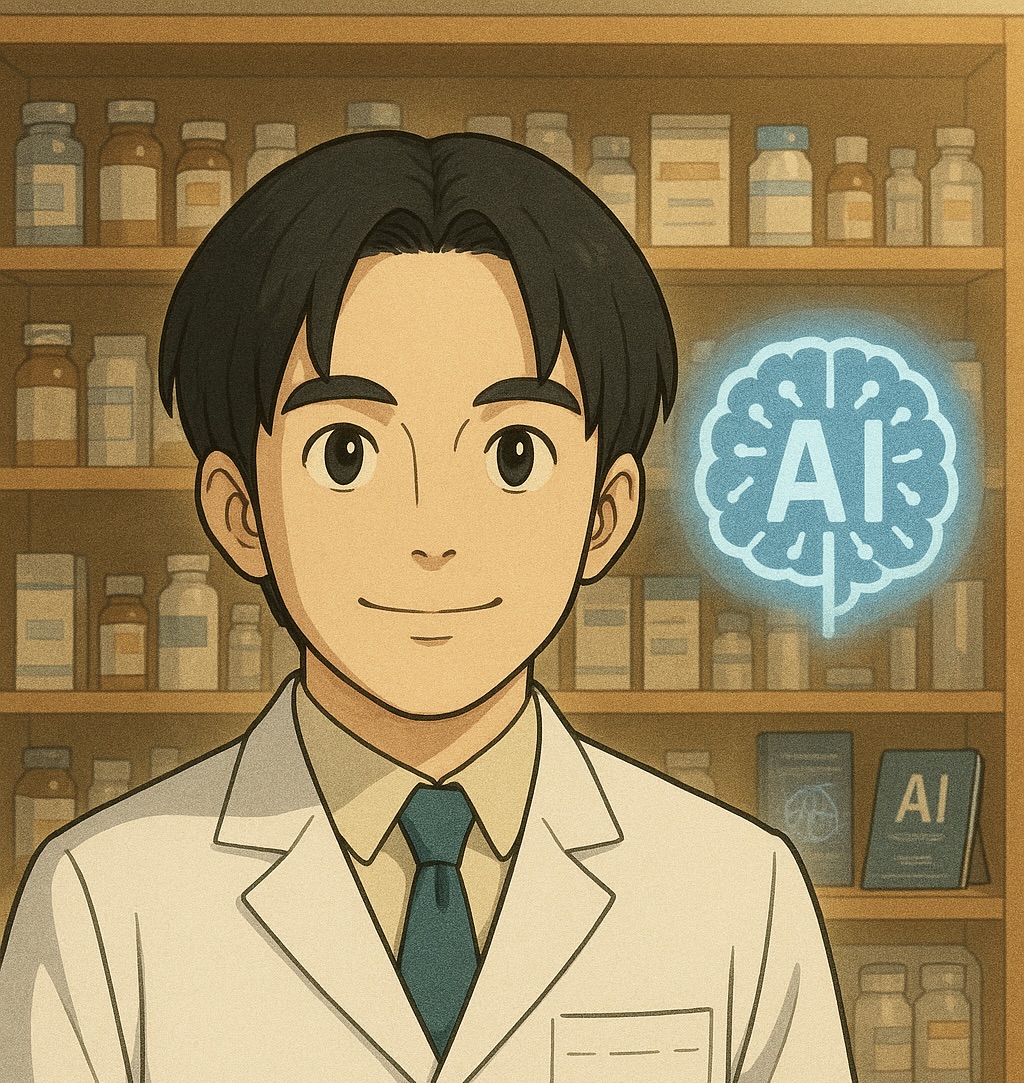
AIが誤った情報を出力してしまうことを「幻覚(ハルシネーション)」と呼びます。
個人情報や機密情報は入力しない
当たり前のことですが、個人情報(名前、住所、マイナンバーなど)や企業の秘密情報を入力しないようにしましょう。一度入力した情報は取り消せないこともあるため、慎重に使うことが必要です。
AIの学習元(データ)は偏っていることがある
AIは「過去のデータ」から学んでいます。つまり、古い情報や偏ったデータを学んでいる場合もあり、公平な判断ができないことがあります。たとえば、ある特定の性別や職業に偏ったアドバイスをする可能性もあります。
対策としてAI自身に「この内容に偏りはありますか?」「別の視点で説明できますか?」と聞いてみるのも有効です。意外と別の角度の答えを返してくれます。
AIを使う目的を明確にする
「なんとなく使ってみる」よりも、「○○を効率化したい」「○○について情報を集めたい」と目的をはっきりさせて使う方が、効果的に活用できます。AIは万能ではないので、「できること」「できないこと」を理解したうえで使いましょう。
薬剤師のAI活用術
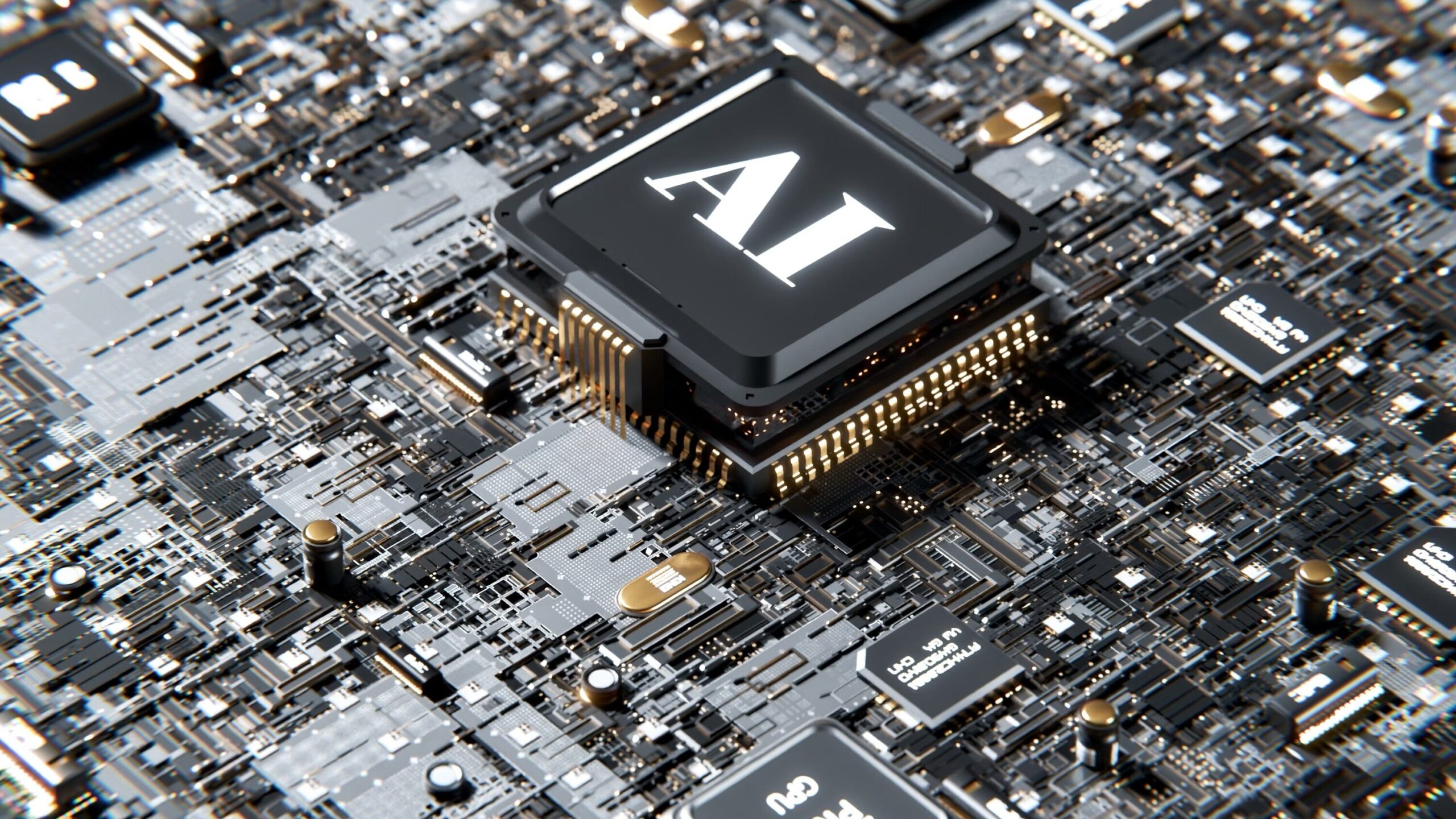
この章では実際に薬剤師がAIをどのように活用できるのか、「業務」と「自己学習」の観点から具体例を交えてご紹介します。
業務でのAI活用方法
1. 薬歴の下書き作成
簡潔で理解しやすい構成が求められる薬歴においても、AIが文章作成をサポートしてくれます。AIに「どのような患者に対して、どのような指導を行なった」と入力するだけで、薬歴の下書きを自動生成してくれます。
例えば、
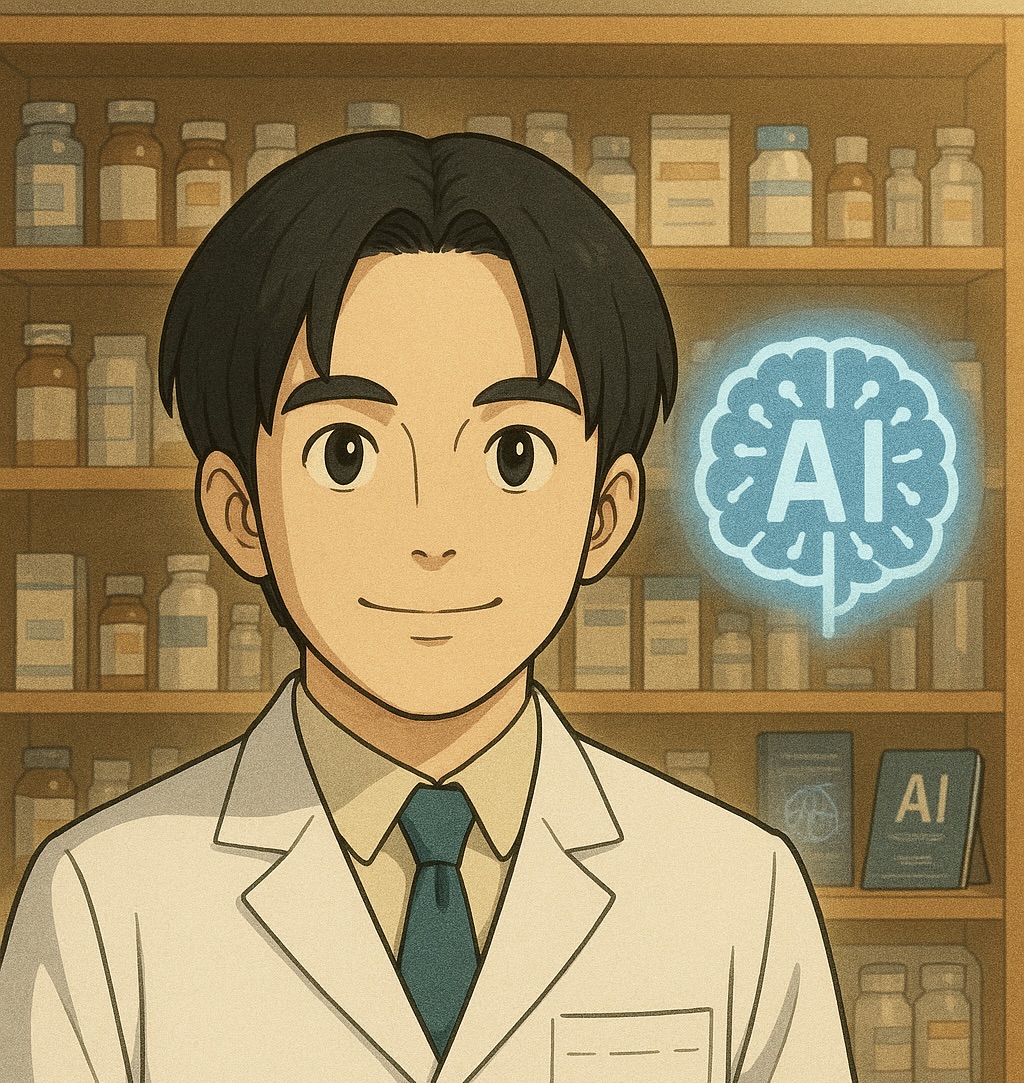
高血圧治療中で顔面紅潮が発現したことで不安を訴える患者に、アムロジピンの副作用説明と服薬継続の必要性を説明した。

S(主観的情報)
患者より「アムロジピンを飲み始めてから顔が赤くなる感じがある。副作用ではないか心配」と訴えあり。
O(客観的情報)
・処方薬:アムロジピン5mg 1錠 朝食後
・バイタル情報:特記事項なし(または確認中)
・他院・他薬局からの薬の併用:なし(必要に応じて記載)
A(アセスメント)
アムロジピンの血管拡張作用による顔面紅潮の可能性。よく見られる軽度な副作用であり、重篤なものではないと考えられる。服薬中止による血圧コントロール不良のリスクの方が高い。
P(計画)
アムロジピンの副作用として顔面紅潮はよくあるが、多くは一時的で重篤なものではないことを説明。必要に応じて医師に相談可能であることを伝え、まずは継続するよう指導。次回来局時にも様子確認を予定。
いかがですか。
多少の手直しは必要ですが、薬歴の下書きとしては十分ではないでしょうか。
さらに詳しい情報や「もっとこうして欲しい!」などのリクエストを付け加えることで、文章のクオリティが向上します。
2. 服薬指導の資料作成・説明補助
お薬や日常生活の注意点などの説明を行う際には、視覚的に理解しやすい補足資料があることでより理解が深まります。しかし分かりやすい文章や図解を作るためには、ある程度のスキルと時間が必要です。
そこでAIを使えば、患者の年齢・疾患・使用薬剤に合わせた説明資料や服薬指導文を一瞬で自動生成することができます。特に高齢者や多剤併用患者に対して、説明を行う際の補足資料として活用できます。
例えば、
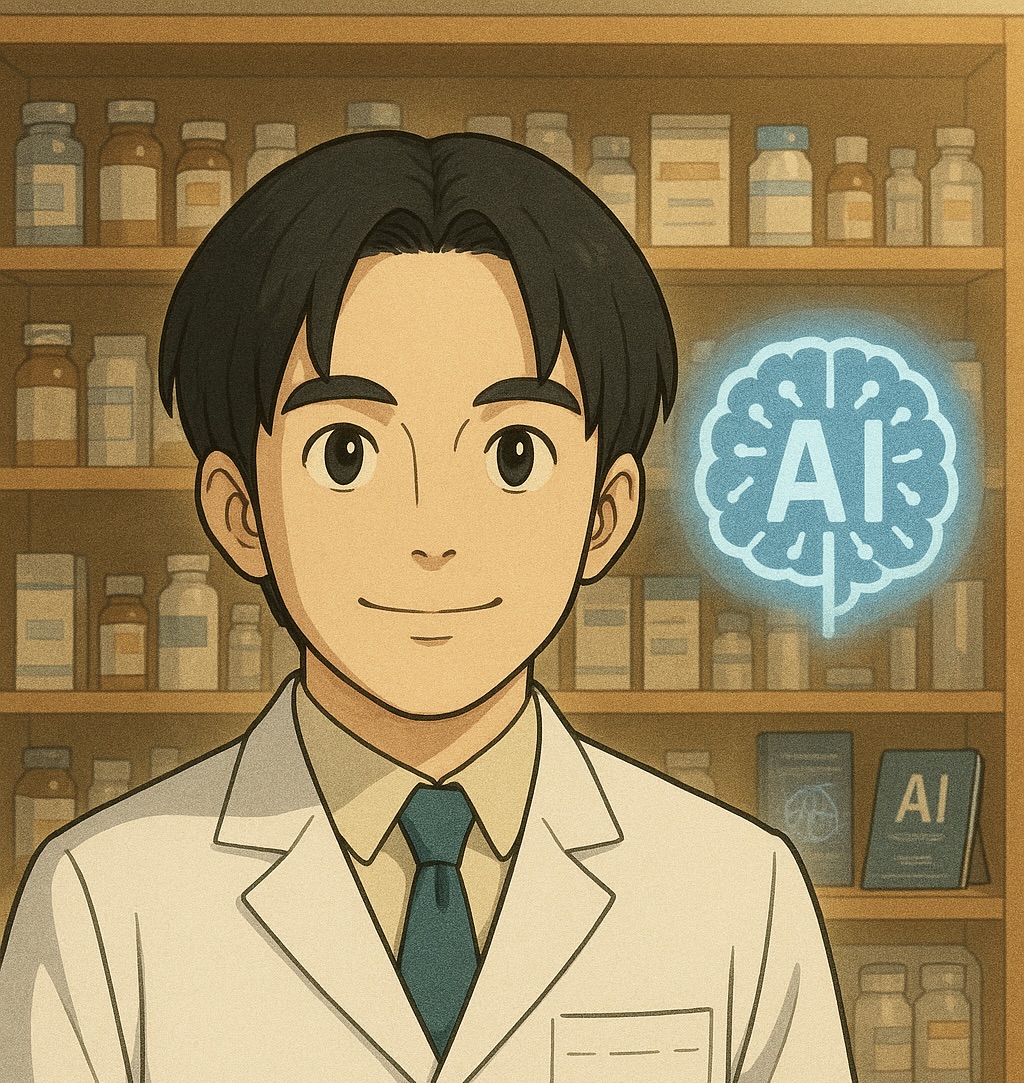
高齢者の糖尿病患者に対して、服用意義を訴えかける資料を作成して下さい。

「糖尿病のお薬、なぜ大切か」
痛くないからといって、安心ではありません
糖尿病は、静かに進む病気です。
「特に困ってないし、飲まなくても…」
そう思っても、体の中では血管が少しずつ傷んでいるかもしれません。
こんな症状、予防できるんです
糖尿病を放っておくと、以下のような症状が現れることがあります
| 合併症 | 起こると… |
|---|---|
| 👁 目の病気(網膜症) | 見えづらくなり、失明することも… |
| 💉 腎臓の病気(腎症) | 人工透析が必要になる場合もあります |
| 🦶 足のしびれ(神経障害) | 感覚が鈍くなり、ケガや壊疽のリスクも |
| 🧠 心臓や脳の病気 | 心筋梗塞や脳卒中の原因にもなります |
➡ でも、お薬をきちんと続けていれば、多くのリスクは防げるのです。
血糖値が落ち着いているのは、お薬のおかげかもしれません
「血糖値が良かったから、もう飲まなくていい」
それは大きな誤解です。
お薬が効いているからこそ、血糖値が安定しているのです。
自己判断でやめると、また血糖値が上がってしまいます。
飲み忘れを防ぐ、かんたんな工夫
- 毎日決まった時間(朝食後など)に飲む習慣をつけましょう
- カレンダーやお薬カレンダーにチェックを入れる
- ご家族や訪問介護の方に声かけをお願いするのもOK
- ピルケースやスマホの「飲み忘れ防止アラーム」も便利です
不安があるのは当然。遠慮せずご相談ください
「副作用が心配」「数が多くて大変」
そんな時は、主治医・薬剤師に何でもお話しください。
一緒に、無理なく続けられる治療方法を考えていきましょう。
最後に…
お薬をきちんと続けることは、
➡「転ばずに歩ける」「ごはんがおいしい」「孫と遊べる」
そんな元気な毎日を守ることにつながります。
高齢者の方でも理解しやすく、上手く服用を促す内容になっていますよね。この文章をPDFにまとめることも可能なので、患者様に手渡す補足資料として活用することができます。
自己学習でのAI活用方法
AIを適切に活用することで、独学の時よりも格段に自己学習の効率と質が上がりました。以下に自己学習でのAI活用方法をご紹介します。
1. AIを先生代わりにする
AIといえば、どんな分野の質問でも答えを用意してくれる先生のような存在だと感じている方も多いのではないでしょうか。AIを各分野の専門家として気軽に質問することができるようになったことで、自己学習中の疑問点をすぐに解決することができるので学習効率が格段に向上しました。
しかし先ほども説明をしましたが、AIの回答は全てが正しいとは限りません。よってAIの回答についてファクトチェックを行う必要があります。ファクトチェックと言っても簡単で、質問の末尾に「信頼できるソースに基づいてファクトチェックしてください」と付け加えるだけで、より正確性の高い回答をしてくれます。
1. 論文要約
AIは要約力にも長けています。「この論文、長いし、難しすぎる…」と感じたら、論文のPDFをAIに添付するだけで要約をしてくれます。さらに論文について質問を投げかけると、論文の内容に則した回答が得られます。
もちろん英語論文にも対応しているので、英語が苦手な方でも簡単に英語論文の内容を理解することができます。AIの登場で個人がアクセスできる情報の幅が広がりました。AIを使いこなして更なる知識のアップデートを目指しましょう!
2. 学習計画の立案
自己学習において学習計画を立てることは重要ですが、学習計画の作成には時間と労力がかかりますよね。そこでAIに学びたい分野と学習期間を入力すると、効率的な学習計画を提案してくれます。
例えば「1ヶ月で糖尿病薬についてマスターしたい」と相談すると、学習の目標や各週ごとの学習すべき内容を考えてくれます。
もちろん学習計画を考えてくれるだけでなく、演習問題の作成や学習のポイントも教えてくれるので、とても効率よく学ぶことができます。
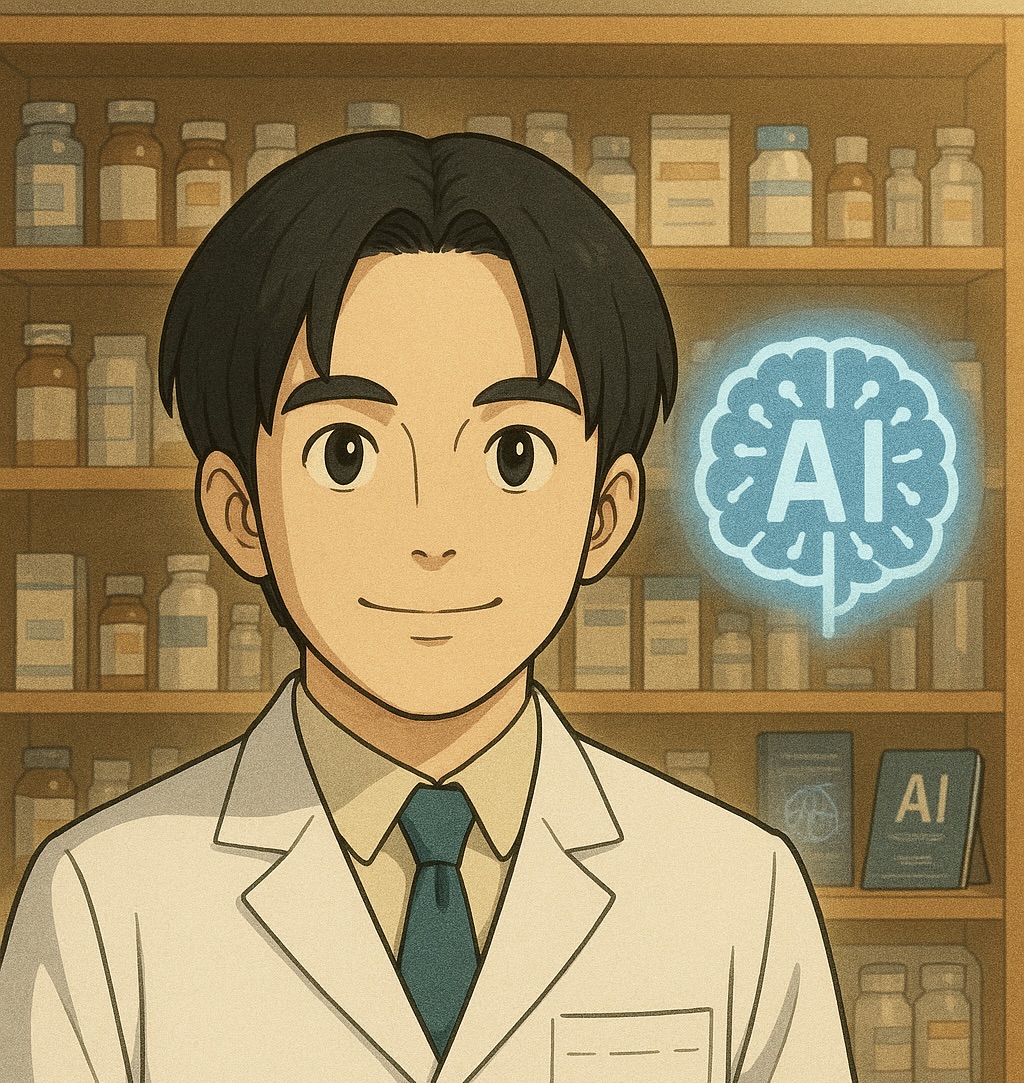
1ヶ月で糖尿病薬についてマスターしたいです。
学習計画を作成して下さい。

全体目標
1ヶ月で糖尿病治療薬の作用機序・適応・副作用・禁忌・薬物相互作用・処方鑑査ポイントを習得する
前提条件
- 対象者:薬剤師または薬学生(ある程度薬理・病態の知識あり)
- 学習時間:1日1時間以上(週5日以上)
- ゴール:実務で「糖尿病薬の説明・鑑査・選択理由の把握」が自信を持ってできる
学習スケジュール
Week 1:総論と薬剤分類の理解
| 日 | 学習内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 1 | 糖尿病の病態(1型・2型、インスリン抵抗性、合併症) | 病態を理解すると作用機序が覚えやすくなります |
| 2 | 治療方針の概要(食事・運動・薬物療法) | ガイドラインでの薬物治療の位置付け |
| 3 | 薬剤の分類と一覧(インスリン系/非インスリン系) | 8クラスに分類して概観をつかむ |
| 4 | ビグアナイド系(メトホルミン) | 第一選択薬、作用機序・副作用(乳酸アシドーシス) |
| 5 | スルホニル尿素薬/グリニド系 | 使い分け、低血糖リスク、作用時間 |
| 6 | 復習+理解度チェック(簡易テスト) | 自作orこちらで問題提供可能です |
| 7 | 休養or補習日 | 疲れた日は軽い復習でOK |
Week 2:非インスリン系薬の深掘り①
| 学習内容 | 補足 | |
|---|---|---|
| 8 | DPP-4阻害薬(シタグリプチンなど) | 高齢者にも使いやすい、副作用(膵炎など) |
| 9 | GLP-1受容体作動薬 | 週1製剤、体重減少効果、注射剤の特徴 |
| 10 | SGLT2阻害薬 | 心保護・腎保護、脱水・尿路感染に注意 |
| 11 | α-グルコシダーゼ阻害薬 | 食後高血糖改善、小腸での作用、ガス・腹部膨満 |
| 12 | TZD(ピオグリタゾン) | 体重増加、浮腫、心不全のリスク |
| 13 | 複数薬剤の比較まとめ | 表形式で特徴・禁忌・副作用を整理 |
| 14 | 休養or症例レビュー | 実際の症例で使い分けの練習をすると |
Week 3:インスリン製剤と実践的知識
| 日 | 学習内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 15 | インスリン製剤の種類と分類(超速効型〜持効型) | 製品名・開始時間・持続時間など |
| 16 | インスリンの使い方(強化療法・混合製剤など) | 初期導入・増量方法 |
| 17 | インスリン自己注射指導と保管・副作用 | 実務でよく聞かれるポイント |
| 18 | 経口薬+注射薬併用療法 | 実例と注意点 |
| 19 | 処方監査のポイント(禁忌・相互作用) | メトホルミン×造影剤など |
| 20 | 糖尿病治療のガイドライン(JDS・ADAなど) | ファーストチョイスや併用の考え方を確認 |
| 21 | 休養+過去2週間の総復習 | クイズ形式・フラッシュカードで確認 |
Week 4:総仕上げとアウトプット
| 日 | 学習内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 22 | 症例ベース学習①:肥満・若年患者 | どの薬を選ぶ?なぜ?を考える |
| 23 | 症例ベース学習②:高齢者・腎機能低下 | 実務的な禁忌・注意点 |
| 24 | 症例ベース学習③:多剤併用・低血糖あり | 薬の見直しポイント |
| 25 | よくある質問と患者説明力の強化 | 「太りますか?」「副作用は?」 |
| 26 | 自作チェックテスト・○×クイズ | 50問以上作ると効果的 |
| 27 | 模擬服薬指導・薬歴記載練習 | 実践のイメージでアウトプット |
| 28 | 総復習&今後の応用計画 | 新薬や合併症対策へ発展させる準備 |
継続と定着のために
- 毎週1回は復習とアウトプット
- ミニテストを自作 or AIに作成依頼する
- 患者説明・服薬指導を想定して学ぶと◎
とても具体的な学習内容と小テストの実施などで脳に知識が定着しやすい学習計画を提案してくれます。続けて「今日からお願いします。」と入力すると、学習計画に沿って1日目からスタートすることができます。
まとめ
AIについての理解が深まるにつれ、その可能性にさらなる魅力を感じた方も多いのではないでしょうか。これからの薬剤師は、ただ薬を渡すだけでなく「AIを使いこなせる専門職」として、新しいステージに立つ時代だと考えています。
誰でも最初は初心者です。ですが最初は何から手をつけるべきか迷うはずです。そんな時には、まずAIに日常で疑問に感じていることを質問してみることから始めてみて下さい。どんな質問でも受け止めて真剣に答えてくれるはずです。
AIが登場したことで知識格差は縮まりました。よってこれからは、AIを使いこなせる人と使いこなせない人との差が格段に広がることでしょう。あなたはこの状況に危機感を持ち、動き出すことができるでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございます。このブログでは、今後も薬剤師に向けてAIに関する情報やAI活用術を紹介していきます。AI時代における理想の薬剤師のあり方を一緒に考えていきましょう!
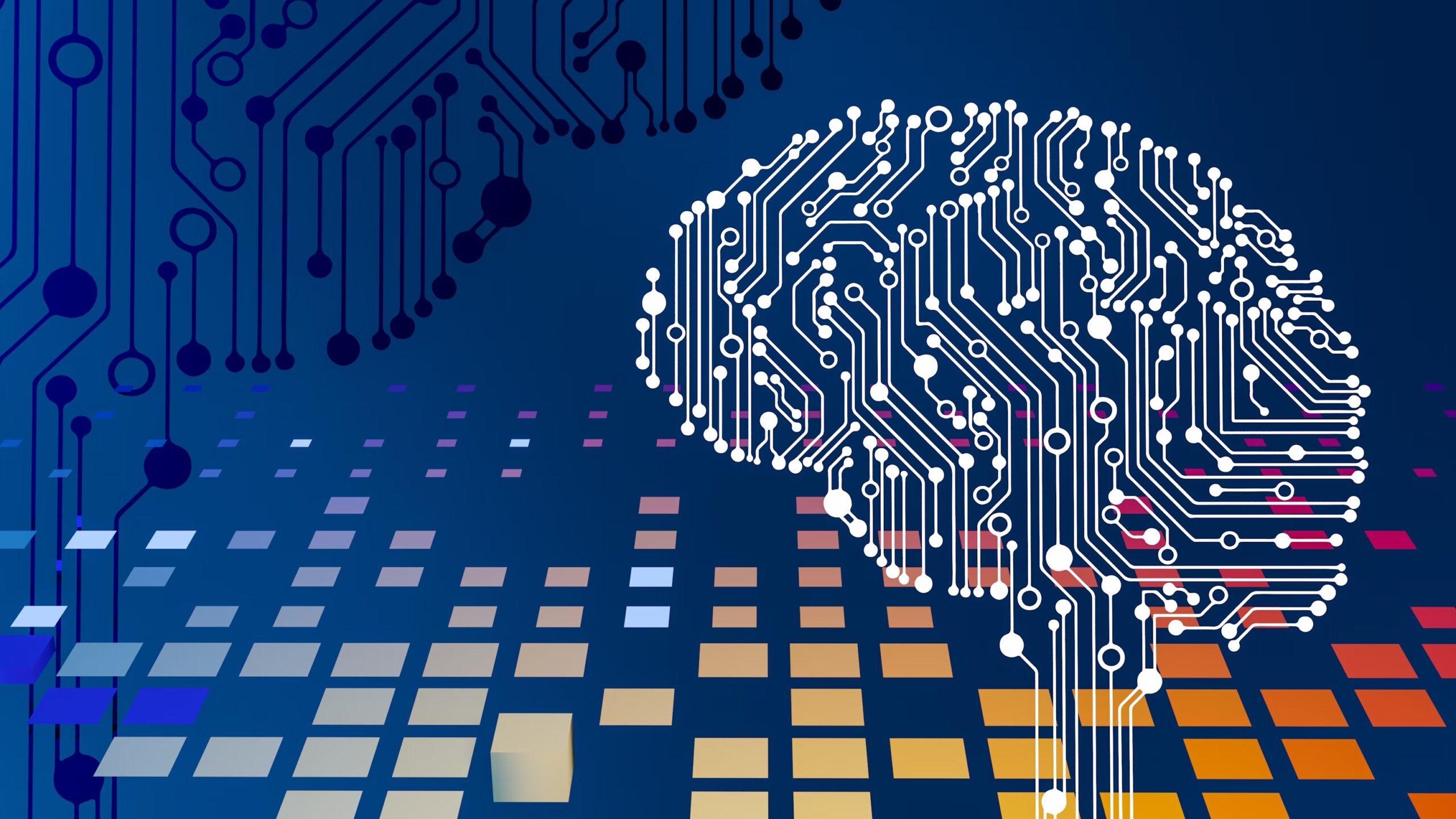


コメント